PR広告広告掲載について
「城福浩監督 就任記者会見」を行いました!【後編】

| 城福浩監督 | Q)城福監督は試合中にチームカラーのマフラーを首に巻いていますが、今度は紫のマフラーを準備していますか。 A)チームスタッフから来年の最新のユニフォームカラー(の情報)を手に入れました(笑) Q)これまでカップ戦のタイトル獲得や甲府をJ1残留に導いたことなど良い時期があった反面、負けが続く苦しい時期がありました。良い時期と悪い時期を経験したことで学んだことはありますか。 A)もちろん良い時も苦しい時もありました。自分にしか見えない景色がありました。ひょっとしたら、それは天空の青だったかもしれないし、深海の青だったかもしれない。ただ、それは自分にしか見えてこない。なぜ天空の青が見えたのか。なぜ深海の青が見えたのか。自分なりに分析はしているし、自分の経験にもなっている。先ほど言ったように自分の信念もありますので、その信念と照らし合わせながら、この経験をすべてこのチームにぶつけたいと思っています。今、ハッキリ言えるのは、何よりも自分が楽しまないと選手は楽しめない。これだけはハッキリ言えます。 Q)サンフレッチェは育成型クラブとしても定評がありますが、若手の育成についてはどのように考えていますか。 A)そういう歴史があって、育ってきた若手がピークパフォーマンスの時に栄冠を勝ち獲ったサイクルがあったと思います。そこを取り戻すのは十分に認識しています。私も若手の育成は大好きな部類でもあります。ただ、彼らに特別な試合の時間を用意することが必ずしも若手の育成になるとは思っていません。彼らも自分で勝ち取る。まず5分を勝ち取る。5分を勝ち取ったら次は15分を勝ち取る。そういうチームでいたいと思っています。それを阻む中堅がいて、それでも時間を増やしていこうとする若手がいる。それには日々の練習から競争が不可欠ですし、試合に出て与えられた時間でいかに自分のチャンスを勝ち取るか。質を出させることが私の役目だと思っています。 Q)育成は短期間では難しいと思いますが、短期と長期で分けて考えた時のそれぞれの目標を教えていただけますか。 A)私は『長期』という単語をのん気に言える立場ではないと思っています。ただ、チームとして若手を育て、その若手が外に羽ばたいていく広島らしさというのも踏まえて、彼らは熱いうちに鉄を叩かないといけない。このチームを成長させるには、今いる戦力の中で激しい競争があって、そこで試合に出る時間を勝ち取っていくことで初めて成長がある。『試合に出します。でも負けてもいいよ』という感じで試合に出ていくことはありえない。試合に出て責任のあるプレーを見せなければ次のチャンスは遠ざかる。それは若手であっても中堅であっても同じことです。その雰囲気を徹底的に作っていくことが短期的にも長期的にもつながっていくと思っています。ただし、志向するサッカーに関しては、おそらく苦しい時もあると思います。サッカーはミスのスポーツなので、『こうやっておけばよかったじゃないか』というシーンがあると思いますが、そこはブレないで続けていくことを自分の中でもやっていきたいと思っています。 Q)監督を引き受けられた決め手を教えてください。 A)まずは足立強化部長の熱意は大きかったです。あとは、サンフレッチェ広島というチームのイメージ、常に自分たちに与えられた条件の中で最大値を出し続ける。それは選手、スタッフ、フロントとサポーターが一体となっているから。そうでなければ成しえない。おそらくクラブの規模からすると、成しえない実績があるのは、そういうことが理由なのかなと外から見て思っていました。もちろん、広島にはよく知ったスタッフもたくさんいるし、よく知った選手もたくさんいる。自分の中で距離感が非常に近かったのもあります。(監督就任を引き受けた)理由は一つではないです。 Q)外で見ていたからこそ分かるサンフレッチェの「こうしたらいいのにな」というポイントがあったら教えてください。 A)『こうしたらいいのにな』というのは、外からならいくらでも言えます。僕はもうそういう立場ではなく、今はインサイドの立場で見ています。やっていれば苦しい時は必ずあると思いますし、良い時も悪い時もある中で、J1で踏ん張って乗り越えてきた。今年の苦しさは来年に生かさないといけないと思っています。具体的に言うと、今季の最終節は伸び伸びとプレーしていたと思います。それは物凄い重荷を背負って戦ってきた33節までがある。それは自分の経験則も含めて、よく分かっています。だからこそ、サッカーの楽しさ、厳しく楽しくやれる環境を早く作ってあげたいと思っています。 Q)今季、リーグ戦を15位で終えた現状を踏まえ、来季の具体的な数字の目標があれば教えてください。 A)数字的なモノは皆さんも期待しているのは十分に承知していますが、目の前の試合に懸ける思いと積み重ねていくモノ。この二つが合わされば、おのずと結果は出てくる。ただし、プレシーズンの期間ぐらいで変えられるハードルであれば、誰しもが変えられています。そんな簡単なモノではない。そこに我々は挑戦したいと思っています。シーズン終盤になってきた時に『確かに変わってきたな』と思われるような、そういうことが少なくてもお見せできるように。でも目の前の試合にはこだわっていくと。その両輪でいきたいと思っています。 Q)城福監督のサッカー観もある中でサンフレッチェの伝統を継承していきたい部分はありますか。 A)サンフレッチェはサッカーと向き合っています。語弊があるかどうかは分かりませんが、サッカーで勝負をして、サッカーで存在感を見せないと大都会のクラブと対等以上に伍していくことはなかなか難しい。それを選手やクラブが本当によく理解している印象があります。ですから、サッカーに向き合わせることにエネルギーをかける必要は私はこのクラブにないと思っています。それぐらい、サンフレッチェのDNAにはサッカーが染み込んでいる。今年、何があって何がなかったかというよりは、選手が流出するのを毎年克服してきた中で、そうそう毎回うまくいくものではない。今年はたまたま苦しい時期があったかもしれないですが、それまでのサンフレッチェはいろんな苦しい立場を乗り越えてきた。これはどんな局面においても全員がサッカーファーストで向き合ってきたということ。選手、フロントが一枚岩になり、そこが崩れない。私は外から見ていても素晴らしいと思っていました。その一員になりたいですし、より強固にしていきたいと思います。 Q)日本だけでなく世界にも多くのクラブがある中で、他の監督には負けていないストロングポイントを教えてください。 A)私はそれは世の中の露わにならない部分で選手が思ってもらえるモノだと思っています。外には出ないモノで、一緒に戦った選手が私と一緒に過ごしてどう思ってくれるのか。それが一番、正直なモノです。それこそが自分の勝負どころでもあります。もしそれがポジティブなモノであれば、私の宝になります。監督と選手の間柄ではなくなっても、そういう思いを抱いてもらえるような指導者になりたいと常々思っています。『ここがストロングだ』と自分ではなかなか言いづらいですが、選手に『もう一度仕事がしたい』と思ってもらえるような環境を築きたい。それを目標にしています。 Q)今季は得点力が課題でしたが、2018年はどんな攻撃を見せたいですか。 A)もちろん流れの中でいくつもの形を持つこと。それはカウンターかもしれないですし、遅攻かもしれないですが、ボールを握ることを恐れず、主導権を握りながら攻めること。『それが特長だな』と言われるチームにしたいですが、カウンターがないチームは怖くないので、もちろん両方を目指したいと思っています。ただし、今年は少しチームのことを調べたら、最初に失点してそのまま負けてしまう試合数がリーグワースト2だった。また、セットプレーでの失点が非常に多い。セットプレーの得点より失点のほうが3倍もある。流れの中だけでサッカーは決まるものではないので、セットプレーの準備もしないといけない。そういう部分で特長のある選手も見極めないといけないと思っています。 Q)シーズン終盤に花を咲かせるために序盤をどのように戦っていきますか。 A)サッカーはリカバリーのスポーツ。誰かがミスをした時、どこかでその状況をジャッジして正しい判断をすれば、そのミスは帳消しになる。どこかで良いプレーをして、それを感じて何人かが反応すれば得点につながる。それをキックオフからやり続けるしかない。『最初は守り倒して』とかそういうことではない。我々が志向する中で、キックオフから一つの状況に対して反応し、ミスもチャンスもカバーする、あるいは生かす集団になること。それが90分続いていくような集団になること。『最初は勝点を取るためにこういうサッカーをします』ではなく、隙のない、あるいは隙を突くような集団にどんどんしていきたいと思っています。 Q)来年、選手やスタッフが集まった際に一番最初に伝えたいことを教えてください。 「ワクワクしているということ。やはり彼らと一緒に作り上げていくというのは、楽しいだけではなく責任も伴います。プレーの責任も伴うし、厳しさも競争も伴う。その中で研ぎ澄まされたチームになっていくというシチュエーションを考えた時にワクワクしますし、それを彼らとともに追求できるのは共有しながらやっていきたいです」 Q)城福監督の「ムービング・フットボール」という信念は、何か大きなきっかけがありましたか。 A)それは自分のサッカーの志向です。もちろん、過去に影響を受けたサッカーや指導者もいますが、もし自分が選手であれば『何が楽しいんだ』というのが根本にあります。その楽しさは状況判断であり、自分たちでジャッジをしながらゲームを進めていくこと。それは攻撃も守備もあると思います。ボールに1回も触らなくて『今日は楽しかったな』と思う選手はいない。どうボールに関わるか。その質の追求も含めて選手が楽しいと感じられるかは、私のイメージの逆算から捉えています。それは、ボールにいかに関わっていくか、いかに判断をともなっていくか。その質が上がっていけばいくほど、サッカーは楽しいと思っています。 Q)プレー以外に時間が許す限りはイベントやメディア露出をおこなってファン、サポーターを増やす努力は必要ですか。 A)昨日広島に来たのですが、たまたまクラブ幹部の方と食事をし、その話になりました。それこそヨーロッパのサッカー先進国の選手たちがどのようにスポンサーやファンの方々に対して接しているのか。そのタイミングはどんなものなのか、議題にしました。日本もそういうものに追い付いていかないといけない。昨日はちょうど論議になり、私も大賛成です。もちろん、タイミングの問題はあるにしても、それは絶対に必要なことです。 |










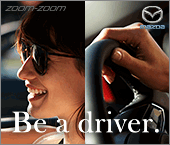
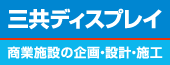






LAST UPDATE:2017/12/22